 都城大弓の歴史
都城大弓の歴史
明治期に弓師・楠見善治が弟子を
養成。昭和初期には一大生産地に
 江戸時代後期の文化・文政時代から天保年間にかけて、当時の都城領の領主・島津家が領内の様子をまとめた書物「庄内地理志(しょうないちりし)」に、都城市内で弓が作られたことが記されています。また、島津家にも御用弓作りの職人がいたことが記録されていることから、都城で古くから育まれてきた工芸であることがうかがえます。明治時代には、鹿児島県から弓師・楠見善治(くすみぜんじ)が都城に来住し、善治やその息子である蔵吉は多くの弟子を養成しました。二人の尽力や、もとより武道具づくりが盛んな土地柄であったこと、そして良質の竹の生産地でもあったことから、昭和初期には外国へと販路を拡大し、一大生産地を形成。最盛期には三十近くの業者が製造に従事していました。現在においては、国内の竹弓の約九割を生産しています。
江戸時代後期の文化・文政時代から天保年間にかけて、当時の都城領の領主・島津家が領内の様子をまとめた書物「庄内地理志(しょうないちりし)」に、都城市内で弓が作られたことが記されています。また、島津家にも御用弓作りの職人がいたことが記録されていることから、都城で古くから育まれてきた工芸であることがうかがえます。明治時代には、鹿児島県から弓師・楠見善治(くすみぜんじ)が都城に来住し、善治やその息子である蔵吉は多くの弟子を養成しました。二人の尽力や、もとより武道具づくりが盛んな土地柄であったこと、そして良質の竹の生産地でもあったことから、昭和初期には外国へと販路を拡大し、一大生産地を形成。最盛期には三十近くの業者が製造に従事していました。現在においては、国内の竹弓の約九割を生産しています。
 都城大弓の魅力
都城大弓の魅力
竹弓ならではの気品
美しい弦音と優れた衝撃吸収性
 都城大弓独自の構造は、大弓の形状を保つとともに強い反発力を生み出します。そのため、放った矢が蛇行せず、直線的に真っ直ぐ飛び、矢を放った後の衝撃吸収性や矢を放った際の弦音(つるおと/弓の弦が鳴る音)の美しさに優れています。また、耐湿性に優れているなど、実践向きであることが最大の特徴といえます。その一方で、大量に生産されるカーボン製などと比べて、竹弓ならではの気品がただようことも魅力の一つとなっています。ある職人は「丹精込めてつくった弓には、製作者の名前を彫り込むため、恥ずかしいものは決して世に出せない」と語ることからも、どれだけ職人さんがこだわりを持ってつくり続けているのかがうかがえます。
都城大弓独自の構造は、大弓の形状を保つとともに強い反発力を生み出します。そのため、放った矢が蛇行せず、直線的に真っ直ぐ飛び、矢を放った後の衝撃吸収性や矢を放った際の弦音(つるおと/弓の弦が鳴る音)の美しさに優れています。また、耐湿性に優れているなど、実践向きであることが最大の特徴といえます。その一方で、大量に生産されるカーボン製などと比べて、竹弓ならではの気品がただようことも魅力の一つとなっています。ある職人は「丹精込めてつくった弓には、製作者の名前を彫り込むため、恥ずかしいものは決して世に出せない」と語ることからも、どれだけ職人さんがこだわりを持ってつくり続けているのかがうかがえます。
 都城大弓ができるまで
都城大弓ができるまで
200もの工程を一人で仕上げる
弓の張り込みが、出来具合を左右
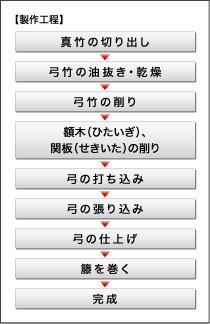 200以上もの工程をすべて一人の職人が手仕事で仕上げる都城大弓。ここでは、都城大弓の作業工程を大まかに紹介します。まずは、弓竹は周囲18~21センチ、真竹は30センチ以上の2種類を切り出し、2~4ヶ月自然乾燥させます。火入れした弓竹は握りの部分を中心にして削り、弓の両端になるほど少し薄くなるように、ムラなく仕上げます。つぎに、弓竹で弓芯を挟み、額木(ひたいぎ/弓の上部分の板部分)、関板(せきいた/弓の下部分の板部分)を付けて接着。80~100本のクサビで締め付けながら、半円状に反りをつけ打ち込みます。その後、クサビをはずし、張り台で弓の型にする。弦を付けて上下の形など出来具合をみながら足で踏んで弓型を整えていきます。弓の善し悪しを左右する大事な工程です。最後に仕上がりを調整し、握りの部分に籐(とう)を巻き完成です。
200以上もの工程をすべて一人の職人が手仕事で仕上げる都城大弓。ここでは、都城大弓の作業工程を大まかに紹介します。まずは、弓竹は周囲18~21センチ、真竹は30センチ以上の2種類を切り出し、2~4ヶ月自然乾燥させます。火入れした弓竹は握りの部分を中心にして削り、弓の両端になるほど少し薄くなるように、ムラなく仕上げます。つぎに、弓竹で弓芯を挟み、額木(ひたいぎ/弓の上部分の板部分)、関板(せきいた/弓の下部分の板部分)を付けて接着。80~100本のクサビで締め付けながら、半円状に反りをつけ打ち込みます。その後、クサビをはずし、張り台で弓の型にする。弦を付けて上下の形など出来具合をみながら足で踏んで弓型を整えていきます。弓の善し悪しを左右する大事な工程です。最後に仕上がりを調整し、握りの部分に籐(とう)を巻き完成です。
| 主な産地・拠点 | 宮崎県 |
| このワザの職業 | 弓師 |
| ここでワザを発揮 | 弓道具 |
| もっと知りたい | 都城弓製造業協同組合 財団法人 都城圏域地場産業振興センター |

